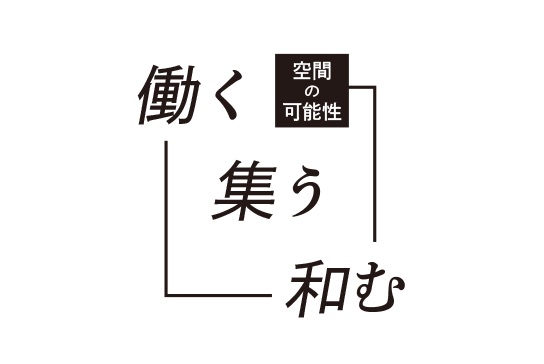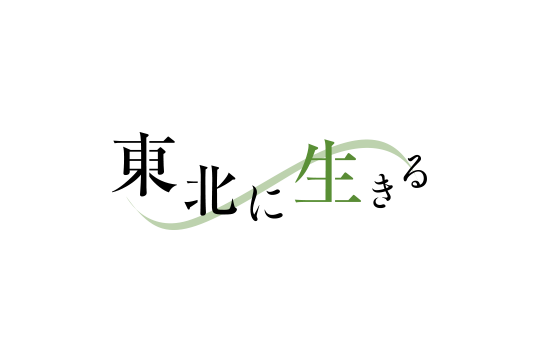株式会社ヘラルボニーがJR東日本スタートアップ株式会社と行った地域福祉連動型・社会貢献型実証実験の第1弾。
JR吉祥寺駅を南北につなぐ「はなこみち」が同社のプロデュースで美術館となった
スタートアップの目利き力(後編)
前編では、経済産業省の経済産業政策局新規事業創造推進室・石井室長に、日本のスタートアップの現状を整理いただいたうえで、水を推進剤とした小型衛星用エンジンを開発するスタートアップ企業・株式会社Pale Blueの浅川純代表取締役に創業の経緯や事業への思いを伺った。後編では、さらに2社、注目のスタートアップ企業を紹介する。
case2
ITとリアルを掛け合わせ第一次産業の新たなインフラを創出する
生産者から直接食材などを購入できるオンライン直売所「食べチョク」を展開する株式会社ビビッドガーデン。同社の秋元里奈代表取締役社長に話を伺った。

同社に生産者から贈られた野菜たち。社内のキッチンで料理しておいしくいただくことも多いという
生産者の「こだわり」を正当に評価したい
生産者が消費者と直接取り引きする「産地直送」は、1960年代に始まったといわれる。もともとは複雑な流通経路を排し、できるだけ安く販売するという思いから始まったため、生産者側のメリットは必ずしも大きくなかった。
「以前の産直ビジネスは、生まれては消え、を繰り返していました。簡単に言えば、まだ土壌が整っていなかった、ということでしょう。しかし、スマートフォンの普及によって誰もが気軽にインターネットを使えるようになったことに加え、フリーマーケットアプリの人気拡大で、C2C(※1)の認知度が高まりました。これなら行けるのでは、と思ったんです」
※1 Consumer to Consumer 個人間取引
と語るのは、生産者から直接食材などを購入できるオンライン直売所「食べチョク」を展開する株式会社ビビッドガーデンの秋元里奈代表取締役社長だ。大手IT企業に勤めていた秋元社長が同社を設立したのは、2016年11月のこと。農家を営んでいた実家に久々に帰省したある日、中学時代に廃業して荒れ果てた実家の農地を見たのが起業のきっかけだったという。子どもの頃には緑豊かだった畑の変わり果てた姿にがくぜんとした秋元社長は、全国各地の農家に話を聞いて回った。

秋元里奈
株式会社ビビッドガーデン
代表取締役社長
1991年神奈川県相模原市の農家に生まれる。慶應義塾大学理工学部卒業後、株式会社ディー・エヌ・エー入社。WEBサービスのディレクター、営業チームリーダー、新規事業の立ち上げを経験した後、独立。2016年ビビッドガーデンを一人で創業。農家や漁師がオンラインで直売できる「食べチョク」を立ち上げ、運営。農業×ITで社会課題に挑む起業家として注目を集める。著書に『365日 #Tシャツ起業家 「食べチョク」で食を豊かにする農家の娘』(KADOKAWA)がある。
「そして思ったのが、中小規模の生産者が、こだわりを持って作った生産物が正当に評価されて販売できる場を提供したいということでした」。形や大きさが規格に合わず大量流通できないものの、生産者がこだわりを持って作り、おいしく育った生産物は決して少なくない。そうした生産物を適正な価格で消費者に届けようというのが「食べチョク」のコンセプトだ。価格は生産者自身が提示する。現在、登録する生産者は6700軒ほど。扱うアイテムは農作物から畜産品、水産物などおよそ4万アイテムに上る。

「食べチョク」は国内の産直通販サイトの中で、抜群の認知度、利用率などを誇り、スマホ用アプリも提供している
投資家との間に不可欠な世界観の共有
創業時の資金は、東京都や銀行からの融資で調達した。
「投資に頼らなかったのは、私たちのビジネスには融資が適していると判断したからです。中小規模の生産者さんがきちんと利益を上げられる仕組みを作るというビジネスは、確立するまでに時間がかかると思いましたので、短期間で成果を求められる投資にはそぐわないと考えました。その後、事業の拡大に合わせエンジェル投資家(※2)などから3回ほど資金調達をしていますが、いずれもご縁があったりご紹介を受けたりしてお会いし、私たちの世界観に共感してくださった投資家さんばかり。新たな価値や社会構造を創り出そうというスタートアップ企業にとって、世界観に共感していただくことは、とても大事なことだと思います」
※2 創業後、間もない企業に資金援助を行う投資家のこと
秋元社長にとって、上場や事業規模の拡大は目指すべきゴールではなかった。何よりも目の前の生産者そして消費者の笑顔を見たい。その積み重ねが、第一次産業の新たなインフラ創出につながると考えていた、という。
「上場が見えてきたころには、インフラづくりが叶うかなと思っていたのですが、まだまだ全然。土俵は思ったより広かった(笑)」
秋元社長はそう笑うが、当初月に数名程度だった「食べチョク」のユーザーは、21年には50万人を突破。国内の産直通販サイトの利用率やアクセス数、生産者認知度など6つのナンバー1を獲得するなど、"ロケット・スタート"と言ってもいい急成長を続けている。「安いから売れるというわけではありません。マーケットプレイスが認知されれば、いいものは適正な価格で取引されることが、これまでやってきて分かりました」と、秋元社長は言う。
課題が多いからこそ可能性を見出せる
こうした業績やサービスは、秋元社長をはじめスタッフが生産者、あるいは消費者の生の声を聞いてきた結果によるところが大きい。同社のスタッフは一次産業や食の業界に貢献したい、という「生産者ファースト」の想いに共感して集まったメンバーだけで運営している。かつてブームとなり、瞬く間にバブルが弾けてしまったITベンチャーは、主にネット上のみでのサービス展開に終始していた点で、現在のスタートアップの潮流とは大きく異なる。「ITと"リアル"をいかに掛け合わせるかが求められているような気がする」と、秋元社長は言う。

第一次産業の新たなインフラを創出しようと、同社のスタッフは生産者の意志を最優先している
一方で、海外との競争激化や従事者の高齢化・後継者不足といった第一次産業の前に横たわる状況は、決して明るいものばかりではない。「確かに課題は多いですが、言い換えればそれだけ伸びしろがあるということ。私たちとしては、『生産者ファースト』の視線を変えることなく、こだわりのモノ作りが正当な評価を受ける仕組みを、確かなものにしていきたいと思います」
新インフラが真のインフラへと成長することができるか。ビビッドガーデンの挑戦は続く。
case3
障害のある人があらゆる領域にコネクトできる社会をつくりたい
株式会社ヘラルボニーは、障害のあるアーティストとライセンス契約を結び、作品を社会に送り出している。松田文登代表取締役副社長に同社の現状、思いを伺った。

松田文登
株式会社ヘラルボニー
代表取締役副社長
1991年岩手県生まれ。大手ゼネコンで被災地再建に従事した後、双子の弟・松田崇弥氏(代表取締役社長)と共にへラルボニーを設立。4歳上の兄・翔太氏が小学校時代に記していた謎の言葉「ヘラルボニー」を社名に、福祉領域のアップデートに挑む。岩手に在住し、ヘラルボニーの営業を統括する。日本を変える30歳未満の30人「Forbes 30 UNDER 30 JAPAN」受賞。
障害は異質という社会の目線を変えたい
岩手県花巻市のJR花巻駅。普段はレンガ調のシックな駅舎が、2019年12月13日から同26日まで、宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』を彷彿とさせる幻想的なアートでラッピングされた。作者の八重樫季良氏は、障害のあるアーティストだ。駅舎をアートでラッピングするというこのプロジェクトを実施したのは、岩手県盛岡市のスタートアップ企業・株式会社ヘラルボニーである。

2020年の釜石線全線開業70周年を記念したラッピング列車。同社と契約する釜石市出身のアーティスト小林覚氏のデザインによるものだ
障害のある作家とライセンス契約を結び、その作品をさまざまな形で社会に送り出していく──簡単に言えば同社の事業をそう表現できるが、プロダクトは実に多岐にわたる。前述した駅舎のラッピングからファッション、インテリア、鉄道車両のラッピング等々。掲げるミッションは「異彩を、放て。」。
「障害のあることは決して異質ではなく、個性です。その個性が創り出した"異彩"を、社会に送り出していくことで、障害がある=異質なこと、という社会の目線を変えていきたい。また、ライセンス料という真水が入ることで、障害のある人、そしてその家族がより幸せになれる。そんな世の中を創りたい」
そう語るのは、同社の松田文登代表取締役副社長。ヘラルボニーが契約するアーティストは海外を含め153名。ライセンシング数は2000作品以上に上るという。
起業のきっかけは美術館での感動と違和感
松田副社長が双子の弟・崇弥社長と同社を設立したきっかけは、もともとアート好きだった崇弥社長が花巻市にある「るんびにい美術館」を訪れたことだった。社会福祉法人が運営する同美術館には、障害のある作家の作品が多く展示されていた。
「彼は単純に作品の素晴らしさに感動した一方で、純粋に芸術作品として素晴らしいのに、社会ではCSRの一環のように扱われていることに違和感を覚えた、と話していました」
というのも、双子の4つ上の兄である翔太氏には先天性の障害がある。生まれた時から当たり前だった兄の個性が異質なものとして扱われる社会の風潮。そのこと自体、双子にとっては長年の疑問だった。
「当初は起業しようなどとは思いもせず、スタートアップという言葉すら知りませんでした。ただ自分たちがやりたいことを続けていく、そして広げていくには、事業として立ち上げた方がいいと判断しました」という松田副社長だが、崇弥社長の提案に、最初は二の足を踏んだという。結婚を控えていたからだ。
「これだけで食べていくのは難しいと当時は思ったのです(笑)」
それでも、社会の目線は少しずつながら変わりつつあるようだ。20年7月には、JR東日本と協業で高輪ゲートウェイ駅の駅前開発の工事現場で、仮囲いを障害のある作家の作品でラッピングするプロジェクトを実施。再生利用可能な素材を活用した作品は、展示後トートバッグにアップサイクル(※)して販売したところ、瞬く間に売り切れたという。障害があるかないかに関わらず、良いものは良いと適正に評価されることを示し、社会にも大きなインパクトを与えた。
※捨てられるはずだった廃棄物や不要品に新たな価値を与えることで、より次元・価値の高い製品を生み出すこと

高輪ゲートウェイ駅前開発の工事現場の仮囲いがアート作品でラッピングされた。価値が循環するミュージアム「CIRCULATION」プロジェクトの一環
同社の業績自体、ここまで倍々で推移しており、「IPOが通過点、と言えるように頑張りたい」と、松田副社長は決意を新たにする。
22年1月には、ホテル「ハイアット セントリック 銀座 東京」とのコラボも始動し、ファッションブランドとして立ち上がった「HERALBONY」はライフスタイルブランドへと進化しつつある。
協業でより見えてきた新たな世界観の定着
21年11月、JR東日本のCVCであるJR東日本スタートアップ株式会社は、同社と正式に資本提携契約を結んだ。同社の柴田裕代表取締役社長は語る。
「社会の課題を解決しよう、地方創生を進めようといった、私たちJR東日本グループとヘラルボニーさんの目指すものの方向は同じ。公共サービスを提供する私たちには、インフラ・信用力・人材という資源がある。それらとスタートアップ企業のパッション、アイデアが結び付くことで最強のシナジー効果が生まれると思います」
ヘラルボニーが地元・岩手に拠点を置き続けることは、地方創生にもつながる。「社会にインパクトを与えることで、例えば障害のあるアーティストの聖地として、宮沢賢治や盛岡の冷麺のような、岩手の観光資源の一つになれれば」と松田副社長。
ちなみに、ヘラルボニーとは兄の翔太氏が7歳の時に自由帳に書き続けた言葉。意味は不明だそうだが、いずれ意味を持つかもしれない。
「社会の目線を変え、いずれは芸術作品だけでなく、飲食やホテルなどといったあらゆる領域に障害のある人がコネクトできる社会をつくりたい。そんな世界観を表すものとして『ヘラルボニー』という言葉が定着するようにしたいですね」その思いを起点に、社会は少しずつ、だが着実に変わりつつある。