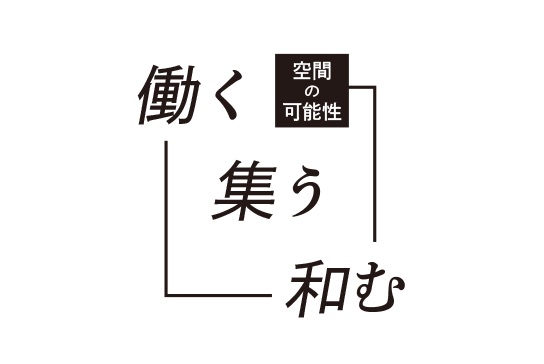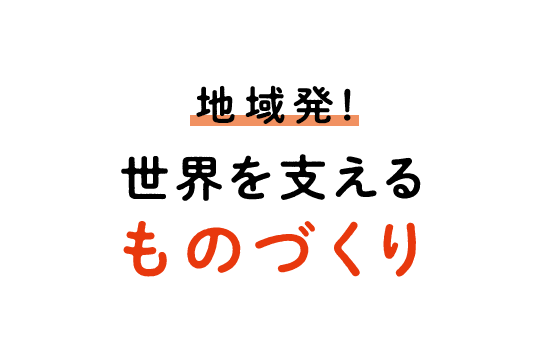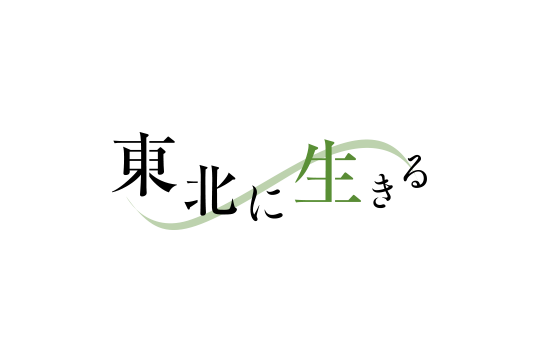「ユニバーサルな社会」の実現に向けて
Case.2 食べやすさだけではなく、食べる喜びも、多くの人に届ける──合同会社楽膳
「ユニバーサルデザイン=障がいがある方向けのデザイン」と思われがちだが、実際はそうではない。そうした先入観を覆す「楽膳椀」を世に送り出した合同会社楽膳の取り組みを紹介する。
食事がしたいと思える器を目指した「楽膳椀」
福島県会津地方で400年以上続く会津漆器。福島市にある合同会社楽膳が販売している「楽膳椀」は、その会津漆器のお椀の底部にくぼみを設けることで、誰もが使いやすいお椀にしたものだ。2006年に販売を開始して以来、根強い人気を保ち続けている。
このお椀のデザインを手がけたのは、同社代表社員の大竹愛希さん。大竹さんは東京の大学に在学中、授業でユニバーサルデザインの考え方と出合い、専門学校に入り直してデザインの勉強をしたという経歴の持ち主だ。そして卒業後は故郷の福島に戻り、お椀のデザインに取り組むことになる。

合同会社楽膳代表社員の大竹愛希さん
「私の両親は、福島で障がいのある方の社会参加を促進するためのNPOを運営しているのですが、その団体の中に、手に障がいがあるためにコップやお椀が持ちづらい菅野さんという方がいます。私は専門学校時代にも持ちやすいお椀の製作に挑戦したことがありましたので、これを完成させることにしたのです」(大竹さん)
大竹さんは、デザインを会津漆器の木地師(※1)のところに持っていった。デザインではお椀の底部にくぼみを入れることにしており、この工程は刃物を使った手作業になるため大変な手間暇がかかるが、引き受けてくれたという。
「実はその木地師さんのお父様も、病気の後遺症で手が不自由になっており、お父様のためにもつくりたいと、私たちと思いを共有していただけました」
協力を受け、できた試作品を菅野さんやお年寄り、子どもなどさまざまな人に試してもらい、改良を重ねた末に楽膳椀は完成した。
「木地師さんのつくった楽膳椀を、お父様もずっと使い続けてくれたそうです」
大竹さんは、こうした経験を通じて、ユニバーサルデザインへの考え方が少し変わったという。
「ユニバーサルデザインとは、完成した製品そのものを指すだけでなく、障がいのある方もない方も、みんなで知恵を出し合いながら少しでも使いやすいものをつくろうとする、そのプロセス自体のことをいうのではないか。そう考えるようになったのです」

お椀の底にくぼみを設けることで、握力が弱くても使いやすくした「楽膳椀」。近くで見ると、くぼみがいかに滑らかにつくられているかが分かる
ちなみに大竹さんが食器の中でも漆器を選んだのは、障がいの有無に関係なく、誰もが「このお椀を使って食事をしたい」と思える高級感のある器をつくりたいと思ったからだ。例えば素材にプラスチックを用いると、急に「介護用の食器」というイメージが強くなる。これでは健常者は使いたいと思いづらく、高齢者や障がいのある方にとっても、食事が楽しいものではなくなってしまう。当時はまだ「ユニバーサルデザイン=障がいがある方向けのデザイン」と見られることも多かったため、こうした誤解が生じることは避けたいと考えたのだ。
また漆器の素材である木は、熱伝導が緩やかであるため、高温の汁を入れて手にしたときでも、熱さを感じにくいことも魅力だった。さらには会津漆器の木地師や塗師(※2)といった職人との出会いも、楽膳椀を通じて、会津漆器の良さを広く社会に発信したいという強い思いへとつながった。
「楽膳椀は、高齢になったご両親へのプレゼントや、お子さんが生まれたご家庭への出産祝いに購入してくださる方が多いですね。お客様から『最近、握力が弱くなった母のために購入したのですが、食べこぼしがなくなり、食事も進むようになりました』との連絡をいただいたときには、すごくうれしい気持ちになりました」
大竹さんが手がけた楽膳椀は、食べやすさだけではなく、食べる喜びも、多くの人に届けている。
※1 ろくろで手作業により、木をくり抜いて素地となる丸物をつくる職人のこと。会津漆器では丸物師ともいう
※2 成形された木地に塗りを施し、器として滑らかな手触りをつくり出し、さらに堅固に整える職人のこと